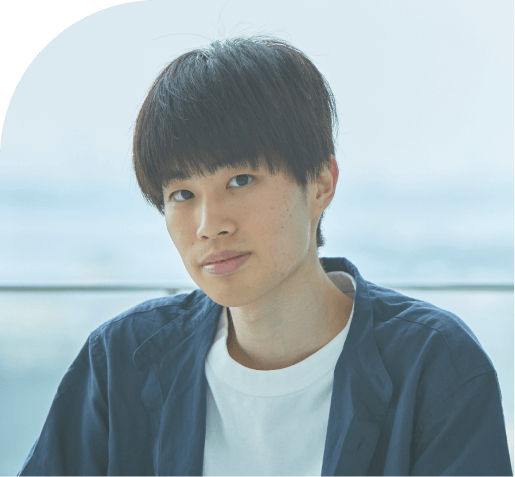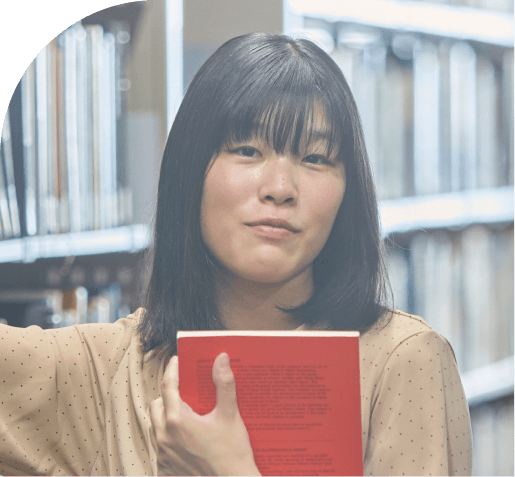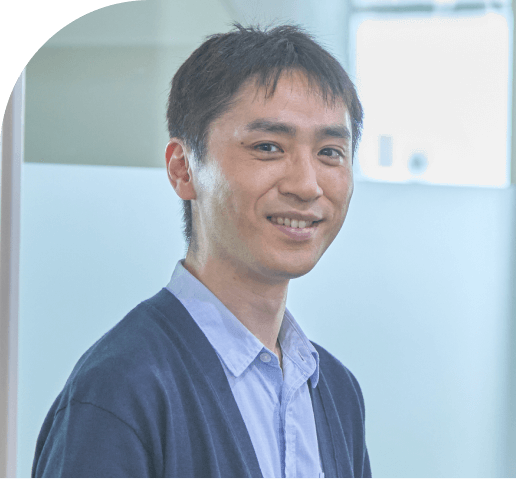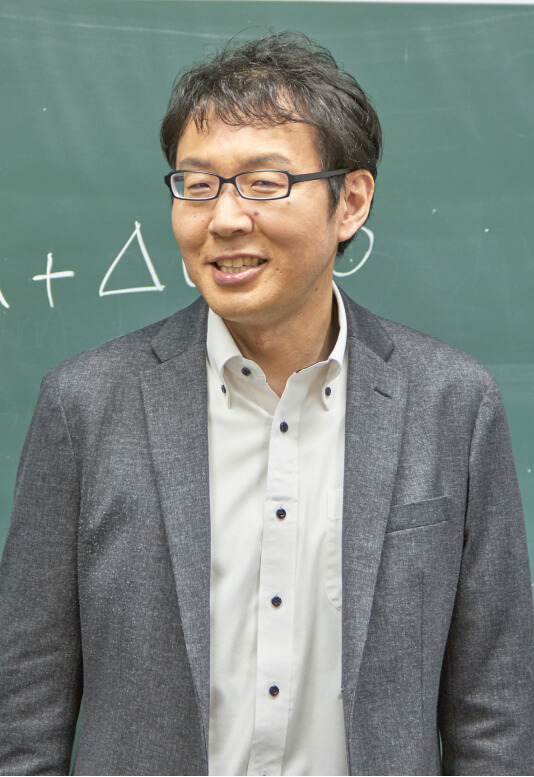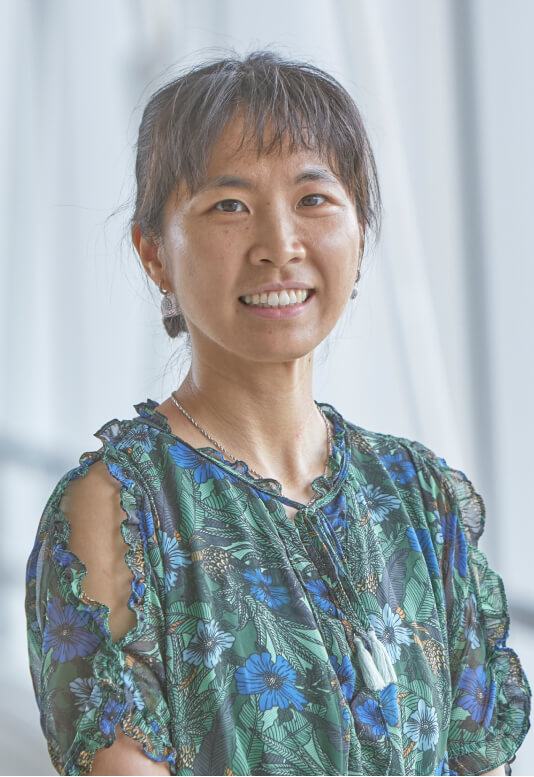数学で人生を豊かに
数学の能力は視覚的にとらえることができません。しかし、それはどの職業に就こうと、どの国へ行こうと、いつまでも消えることなく皆さんの人生を支えてくれることでしょう。九州大学理学部数学科と大学院数理学府では「数学で人生を豊かに」をモットーに数学の多岐にわたる教育と研究を行っています。数学が好きな皆さん、数学に興味を持つ皆さん、ともに数学を学んで楽しみましょう。
メッセージ
About
九大数理で学ぶ
九州大学は数学分野で70名以上の研究者を擁する国内有数の研究教育拠点です。九大数理(理学部数学科・大学院数理学府)では、数学の基礎的な教育から現代数学の頂を極める研究まで多様な活動が行われています。

Future
理学部数学科卒業者

大学院数理学府修士課程修了者

卒業生の多岐にわたる活躍のフィールド
理学部数学科・大学院数理学府の卒業生は、金融・保険や情報技術関係の企業の研究職、学校教員、学術研究者など、多岐にわたるフィールドで活躍しています。数学が社会の様々な場面で使われるようになってきていることが背景にあります。
理学部数学科卒業者
進路状況

大学院数理学府修士課程修了者
進路状況